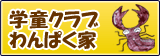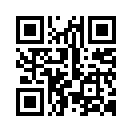2007年06月09日
ワラビー 光る泥だんご
ピカッーと鏡のように光る。自分の顔や雲や太陽まで見える「光る泥だんご」。バカボンの師匠は神森学童クラブで指導員している兼本さん。習った頃は失敗してばかり。失敗にくじけずに何度も何度も作り続けることで「光り方のコツ」がわかってくるのです。今なら約1時くらいでできます。「光る泥だんごづくり」も「体でコツを覚える伝承遊び」なのです

ではバカボン流の作り方を説明します。ほかの本と違うと思いますが気にしないでね。場所で一番いいのは公園、または学校のグランドです。土と砂が混ざった所。きれいな丸にするためです。土が多いとデコボコになりやすく、砂が多すぎるとくっつかない。作りやすいところを探してください
最初は「土台づくり」。小さな山をつくり、ペットボトルの水をドバッとかける。直径3~5cmの水だらけの土砂(つちすな)を何度もしぼり出します。丸くなるように、しぼったものをコロコロ手で転がす。しぼるのはココまでで、後は握ってもダメです
次は「かけて、こぼして、なでる」。一回目は水分が多いので、乾いた土砂を全体に3~4回ほどかけて、こぼして、なでます。「こぼす」のは、小さい石を落とすためです。「なでる」は指で1~2回撫でて、土砂を土台にそっと「くっつける」のです。直径5cmの土台は完成する頃には直径7cm程になっています。細かい層(そう)で成長していくのです。

水分がなくなるまで「かけて…」を続けてゆきます。「水分がなくなる」のは自分の手を見てください。手に水分が付いていると、まだあるということ
水分がなくなった状態で、土台に「細かく乾いた土」をぬりつけます。「細かく乾いた土」は、はじっこのセメントの上あるものです。手にたっぷりと土をなすりつけ、土台に一回軽く塗りつけます。約15分以上つづけると、中に光る泥だんごの表面が少しづつ現れてきます。これがだんこのカラーになります。グランドなら赤茶色、クチャなら黒、大きな木の下なら違う色になります。最後まで磨かずにいることが大切。光度の高い皮膜=芯ができてきます

自分で時間を決めて、ストッキングで磨くと、ピカッー。感動と満足感!大人でもはまっちゃいます。最後に「ビニール袋」に光る泥だんごを入れ、2~3日タオルの上で密封します。土台の中に入っている水分を外に出すためです。ビニール袋に入れなければ次の日には表面が割れてしまいます。冬は夏よりも長く入れる必要があります。
ダダでできる光る泥だんご作り。誰がなんと言おうとも「自分の宝物」なんです


(学童クラブわんぱく家指導員・ONEネット代表)


ではバカボン流の作り方を説明します。ほかの本と違うと思いますが気にしないでね。場所で一番いいのは公園、または学校のグランドです。土と砂が混ざった所。きれいな丸にするためです。土が多いとデコボコになりやすく、砂が多すぎるとくっつかない。作りやすいところを探してください

最初は「土台づくり」。小さな山をつくり、ペットボトルの水をドバッとかける。直径3~5cmの水だらけの土砂(つちすな)を何度もしぼり出します。丸くなるように、しぼったものをコロコロ手で転がす。しぼるのはココまでで、後は握ってもダメです

次は「かけて、こぼして、なでる」。一回目は水分が多いので、乾いた土砂を全体に3~4回ほどかけて、こぼして、なでます。「こぼす」のは、小さい石を落とすためです。「なでる」は指で1~2回撫でて、土砂を土台にそっと「くっつける」のです。直径5cmの土台は完成する頃には直径7cm程になっています。細かい層(そう)で成長していくのです。
水分がなくなるまで「かけて…」を続けてゆきます。「水分がなくなる」のは自分の手を見てください。手に水分が付いていると、まだあるということ

水分がなくなった状態で、土台に「細かく乾いた土」をぬりつけます。「細かく乾いた土」は、はじっこのセメントの上あるものです。手にたっぷりと土をなすりつけ、土台に一回軽く塗りつけます。約15分以上つづけると、中に光る泥だんごの表面が少しづつ現れてきます。これがだんこのカラーになります。グランドなら赤茶色、クチャなら黒、大きな木の下なら違う色になります。最後まで磨かずにいることが大切。光度の高い皮膜=芯ができてきます

自分で時間を決めて、ストッキングで磨くと、ピカッー。感動と満足感!大人でもはまっちゃいます。最後に「ビニール袋」に光る泥だんごを入れ、2~3日タオルの上で密封します。土台の中に入っている水分を外に出すためです。ビニール袋に入れなければ次の日には表面が割れてしまいます。冬は夏よりも長く入れる必要があります。
ダダでできる光る泥だんご作り。誰がなんと言おうとも「自分の宝物」なんです


(学童クラブわんぱく家指導員・ONEネット代表)
Posted by バカボン at 00:24│Comments(3)
│ローテク遊び
この記事へのコメント
スゴイです♪
バカボンさんのうわさは、入童していた友人ママより聞いてました!(安心して下さい素敵な話ですので^^)
子供には、ホント宝物ですね。
バカボンさんのうわさは、入童していた友人ママより聞いてました!(安心して下さい素敵な話ですので^^)
子供には、ホント宝物ですね。
Posted by しんちゃん at 2007年06月09日 02:50
む・・・っちゃくちゃ光ってますね☆
驚いてついコメント入れてます。
これは芸術;だと思います!!!!
ここプリントアウトして駐車場で娘と挑戦しまっす!!
驚いてついコメント入れてます。
これは芸術;だと思います!!!!
ここプリントアウトして駐車場で娘と挑戦しまっす!!
Posted by ひろぶぅ at 2008年04月30日 11:47
はじめまして。ヨヘナともうします。
突然のコメント失礼いたします。
「土団子作り」とてもいいですね。
今朝ラジオを聴いていたら、佐賀県で同じような光る土団子作りをしているお店の事が取り上げられていました。
幼少のころ、自分もよく土団子を作って遊んでいたので、インターネットで検索をしたら、このページを発見し、沖縄でも土団子を作ってる方がいるなんて!と、ついコメントを残したくなった次第です。
このページを参考にし、今度自分も土団子づくりに挑戦したいと思います。
ちなみに、自分が幼少のころ、友人同士で良く土団子を作って、土団子どうしをぶつけ合ってどっちが割れずに残ってるかを競う遊びをやっていました。
その遊びのことを(もしくは土団子じたいを)「てんまーすー」とよんでいました。(記憶がただしければですが・・。)その「てんまーすー」という名前に心当たりありませんか?
私は沖縄市の出身ですが、沖縄市だけの呼び名だったのでしょうか?
では、ながながと失礼いたしました。
突然のコメント失礼いたします。
「土団子作り」とてもいいですね。
今朝ラジオを聴いていたら、佐賀県で同じような光る土団子作りをしているお店の事が取り上げられていました。
幼少のころ、自分もよく土団子を作って遊んでいたので、インターネットで検索をしたら、このページを発見し、沖縄でも土団子を作ってる方がいるなんて!と、ついコメントを残したくなった次第です。
このページを参考にし、今度自分も土団子づくりに挑戦したいと思います。
ちなみに、自分が幼少のころ、友人同士で良く土団子を作って、土団子どうしをぶつけ合ってどっちが割れずに残ってるかを競う遊びをやっていました。
その遊びのことを(もしくは土団子じたいを)「てんまーすー」とよんでいました。(記憶がただしければですが・・。)その「てんまーすー」という名前に心当たりありませんか?
私は沖縄市の出身ですが、沖縄市だけの呼び名だったのでしょうか?
では、ながながと失礼いたしました。
Posted by 饒平名充良 at 2011年11月10日 09:22